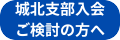危機管理広報・クライシスマネジメントのシリーズ3回目は、前回に引き続き、最低限知っておくべき法務知識のキホンです。
今回は、著作権法および、商標法と不正競争防止法について紹介します。

3.著作権法
著作権法について、文化庁ウェブサイトで次のように説明されています。
著作権法では、著作物を創作した者に権利を付与するとともに、著作物の公正な利用を図るための調整規定を数多く取り入れています。このように、著作権法は、適切な権利保護によって「創作の促進」を図り、権利の制限によって「公正な利用」を確保することで、「文化の発展に寄与」することを目的としています。
※出典:文化庁ウェブサイト
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94215301_01.pdf
著作権法における著作者の権利(著作権)は、知的財産権の一つです。さらに、この著作権は、①人格的な利益を保護する「著作者人格権」と、財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の2つの権利で構成されています。
広報業務では、広報素材として写真やイラスト画像、音楽、動画などの映像、出版物等の文章、学術論文や講演などのコンテンツを使用するケースが頻出します。その使用する素材が他者の著作権を侵害していないか慎重にチェックします。侵害が発覚すると、損害賠償等の法的トラブルだけでなく、企業の信頼を損なうおそれにつながります。そのため、他者の著作物を引用・転載する場合、それぞれのルールの遵守と適切なクレジットの明記をおこなうことになります。
よくある問題として、新聞や雑誌記事を社内イントラで共有する事例があるのですが、これも著作権関連トラブルのひとつです。そのほかには、営業職など広報担当以外の社員が、良かれと思い自社のPR目的で新聞記事やテレビ放送の映像、または雑誌や他の著作物の記事などを配布しSNS等で配信する事例も問題となるケースです。これらの場合、事前の許諾手続きを済ませているか、著作権侵害がないか等、広報担当としても留意し、法務部門とも連携しながら対策を図っておくことが必要となります。
著作権法は、文化庁所管です。
文化庁のホームページでは、わかりやすいテキストや、セミナー映像(自治体向けとなっていますが、十分に視聴の価値がある動画です)も公開されており、全体概要の理解に役立ちますのでおススメです。
■参考サイト(文化庁サイト内):
著作権テキスト(令和7年度版)
●令和7年度都道府県著作権事務担当者講習会の概要サイト
●令和7年度都道府県著作権事務担当者講習会アーカイブ配信中(8月末日まで)
AIと著作権について
さらに、生成AIによる著作物の著作権も気になるテーマです。文化庁では、国の審議会による考え方の進捗を含め、特設サイトやセミナー動画も公開しています。広報担当の方にも基礎的理解に役立つものとしておススメします。
実務では、弁護士や法務・知財部門との連携で対策を図るようにしましょう。
■参考サイト(文化庁サイト内):
●令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」
●令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」
●AIと著作権について(文化庁サイト内ページ)
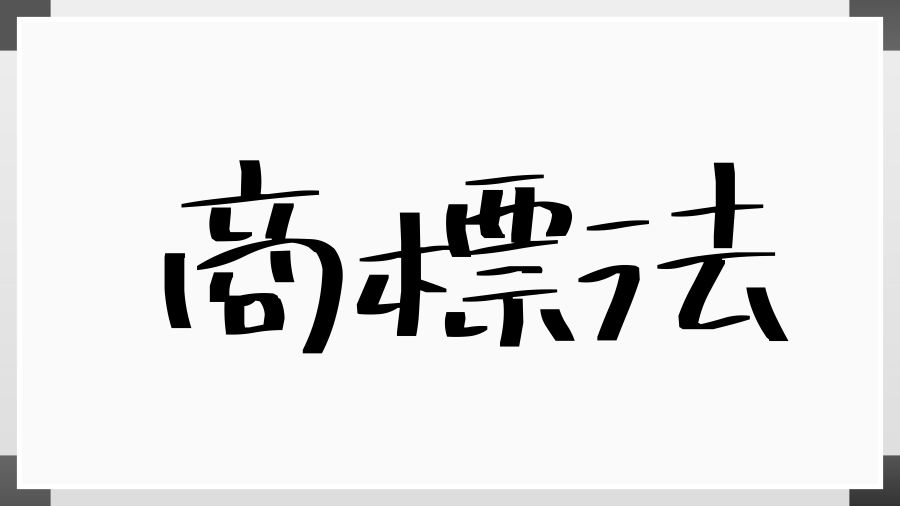
4.商標法と不正競争防止法
(1)商標法
商標および商標法について、特許庁ウェブサイトで次のように説明されています。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。私たちが商品を購入したりサービスを利用したりするときには、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。また、事業者は商品・サービスに「商標」をつけることによって、自社の商品・サービスであることをアピールしています。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
商標法(昭和34年法律第127号)は、このような、事業者が商品やサービスに付ける商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与するとともに需要者の利益を保護することを目的としています(第1条)。
※出典:特許庁ウェブサイト「2024年度知的財産権制度入門テキスト」より
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2024_nyumon/1_2_4.pdf
広報業務として企業ロゴやブランドの商標登録の確認はもちろんですが、新商品・サービス発表時にプレスリリースで®マークや™マークを適切に表示するのも商標権に配慮した広報対応です。また、他社との共同発表の場面でも提携先の企業名や商品名を合意の上で表記するなどの広報業務が発生しますが、これも同様の配慮になります。
インフルエンサーマーケティングを活用している企業もあるでしょう。その場合は、インフルエンサーの発信コンテンツをモニタリングする必要性が浮上するでしょう。例えば、インフルエンサー等による発信内容に自社の商標権侵害につながる表現がある場合は、必要に応じて対応を検討する場合があります。
これらも同じく法務・知財部門との連携で対策を図るようにしましょう。
商標法は特許庁所管です。
■参考サイト(特許庁サイト内):
2024年度知的財産権制度入門テキスト
(2)不正競争防止法
不正競争防止法については、特許庁ウェブサイトで次のように説明されています。
不正競争防止法は、元々はパリ条約を実施するために制定されたものであることから、特許法、商標法等と同様の知的財産法に属すると理解されています。
不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争」を確保することと、「国際約束の的確な実施」を確保することを直接的な目的とし、これにより、「国民経済の健全な発展に寄与すること」を最終的な目的としています。
出典:特許庁ウェブサイト
2024年度知的財産権制度入門テキスト
(第5章その他の知的財産等第1節不正競争の防止(不正競争防止法))
商標法で保護しきれない不正競争行為を不正競争防止法によって規制している、という側面があります。商標法と重なる点として、「周知表示混同惹起(じゃっき)行為」の規制と、「著名表示冒用行為」の規制がある、ということでしょう。
商標法と不正競争防止法は、それぞれの法律の保護対象や権利行使の条件の違いがあるため、広報担当者はこの2つの法務知識をセットで認識しておくのがベターです。
実務では、やはり法務・知財部門との連携が欠かせません。
所管は経済産業省(知的財産政策室)です。
■参考サイト(経済産業省サイト内):
不正競争防止法テキスト(2025年6月公開)
次回も続きます。
東京都中小企業診断士協会城北支部 広報部
田中尚美