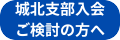広報PR担当者の方には、昨今、企業の不正や不祥事のニュースが増えているように感じている人も多いのではないでしょうか?
専門の調査報告によると、不正の発生状況を、2022年~2024年の3年間の調査対象期間に「不正が発生した」上場企業は32%と約3分の1にのぼっている、と報告しています。(KPMG FAS「日本企業の不正に関する実態調査2024」より)
この調査報告によって、あらためて企業の不正・不祥事問題は他人事ではないと認識できるはずです。くわえて、SNS時代におけるデマや誤報による風評被害と炎上問題も増え、企業価値を低下させるレピュテーションリスクが目立つようになっています。

ここで、さまざまな疑問が生じるのではないでしょうか?
「企業の不正や不祥事、そしてレピュテーションリスクが企業にもたらす不利益は、現実的にどのようなものなのか?」「企業の不正・不祥事やレピュテーションリスクに関して、広報PR活動としてどのような対策や対応が必要なのか?」「BCP(事業継続計画)やリスクマネジメント活動の取り組みは進んでいるけれど、自社の広報PR活動のリスクマネジメントは十分なのか?」など。
本テーマでは、「危機管理広報・クライシスマネジメント」について、広報PR担当者が最低限知っておくべきキホンをおさえておこうと考えます。
「危機管理広報の準備が不十分でこれから着手したい」と考えている方を対象に、前段階となる基本理解をサポートするものです。そのため、自社にとっての専門的・具体的施策の検討については、まずは弁護士や法務部門等の専門家へ相談と確認を進め、連携をはかっていただく必要がある点にご留意ください。
中小企業の広報PR担当者の皆さまが「危機管理広報・クライシスマネジメント」を考えるにあたり、その重要性を理解し、自社の広報PR活動にどのようなことが必要なのかを見直す機会になることを期待しています。
■広報PR活動における「危機管理広報・クライシスマネジメント」の重要性と心構えとは?
昨今の企業のニュースでは次々に社会的影響度の大きい問題が発覚し表出しています。例えば、日本企業の不正が増えているという実態については冒頭の調査報告書の紹介で触れたとおりです。
法令順守違反・コンプライアンス欠如、ガバナンスの不全、物言えぬ組織風土と歪んだ人事労働慣行、横行する不正行為、さまざまなハラスメント、など重大な経営リスクにつながる不正トラブルのニュースは突如として社会的な混乱にまで発展しています。
企業の不信感が高まる不正や不祥事トラブルが社会的影響を大きくしている背景にはいくつかの理由が考えられます。
(1) インターネットとSNSの普及により、瞬時に情報拡散する傾向が強まっている
(2) 消費者の意識の高まりにより、社会の企業への監視圧力が増す傾向にある
(3) 企業への迅速な対応と透明性、倫理性が求められるようになっている
(4) 企業の社会的責任に対して強い関心が集まっている
(5) デジタル化・グローバル化が進展するなかで、新たな法律や規制の導入により対応の強化・厳格化が進み、情報開示義務も増えていること
(6) 世界的な潮流のひとつであるSDGsのような国際的な共通目標の共有と協働も求められるようになっていること
(7) さらに、国際的にも「ビジネスと人権」への急激な関心も高まっていること
などがあげられるでしょう。
企業が直面する不確実性リスクは多岐にわたり、年々増加・複雑化しているといわれます。VUCA時代と呼ばれる今、企業のリスクマネジメントの重要性も増すばかりです。そのリスクマネジメントにおける広報活動、つまり危機管理広報・クライシスマネジメントについて、広報PRの心構えや姿勢のポイントを整理しておきます。
(1) 企業の信用やブランド価値を高める活動である広報PRは、自社のリスク情報について積極的にモニタリングを行うこと
(2) 緊急時の適切で透明性を重視した情報発信を行うこと
(3) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーションと理解を促進と共有化をはかり、信頼を守ること
(4) 危機後のフォローアップと継続的な改善をはかること

■広報PR担当者が法務知識・法務リテラシーを高める意義とは?
そもそも広報PR活動の意義のひとつは、ステークホルダーや社会に対して自社の価値をわかりやすく情報提供し、相互の信頼関係を構築するためのコミュニケーション活動であると、既述のコラムで紹介しました(はじめての広報を応援する 中小企業の広報・PRノウハウ ブログスタート~中小企業にとって広報・PRとは?)。
危機管理広報の重要性は本コラムの上記で述べた通りですが、その意義と法務リテラシー向上の必要性について考えていきましょう。
企業の事件や事故の発生時において、いかに適切な広報対応が遂行されるかは非常に重要なポイントです。その後の企業の信用低下および企業価値低下リスクの最小化に差がついてしまうからです。
企業の不祥事や炎上トラブルで対処を迫られた記者会見は、いまや、一般の方々がさまざまなメディアで会見ライブを視聴することができる時代です。そのなかで、明らかに失敗例であり、企業のマズイ初動や記者会見だと見受けられる事例の多くに共通点があります。それは、生活者を含む社会・ステークホルダーとの「感覚・価値観のズレ」です。さらに企業側の間違ったリスク意識やリスク認識の欠如も見受けられます。
危機管理広報においては、社会・ステークホルダーとの感覚・価値観のズレをなくすよう、常にウォッチしながら、瞬時の判断もできるよう必要な対応策を講じていくこと。これは、危機管理広報における広報PR活動の大きな役割の一つといえます。そのため、担当者は法務知識・法的リテラシーの向上はもちろん、企業を取り巻く時代の価値観の流れにも敏感にキャッチしておくことが欠かせません。
企業の信頼性を高めながらリスクを最小化することは広報PRにも必要な視点です。そのために担当者は法務知識を高め、企業法務活動との連携・補完をはかることが不可欠です。広報PR担当者の法務リテラシーの有無が広報PR活動の質を左右するする重要なポイントといえます。
広報のリスクマネジメント力でいいね!を目指したいものです。
次回は、広報PR担当者が最低限知っておくべき法務知識のキホンに触れたいと思います。
東京都中小企業診断士協会城北支部 広報部
田中尚美