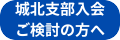危機管理広報・クライシスマネジメントのシリーズ4回目は、前回に引き続き、最低限知っておくべき法務知識のキホンです。
今回は、肖像権・パブリシティ権・プライバシー権について紹介します。
実務では法務・知財部門との連携を必ず図り、具体的対策を進めましょう。
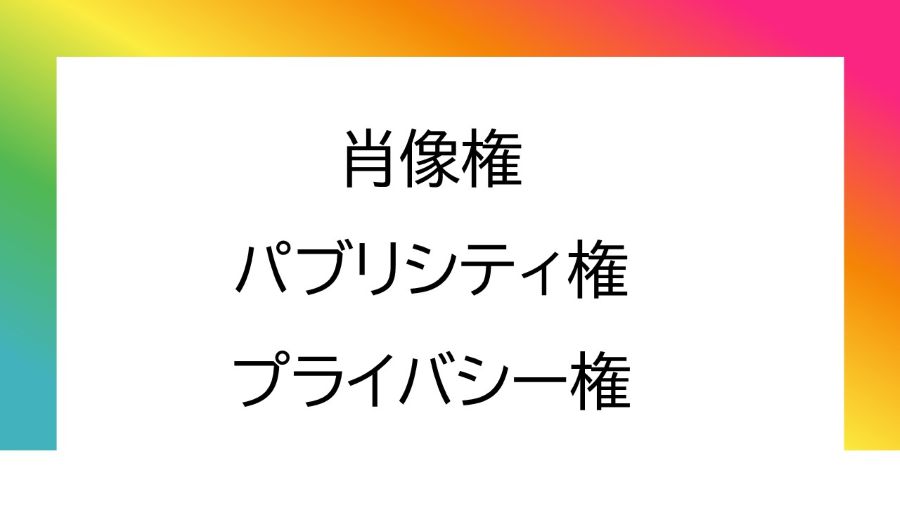
5.肖像権、パブリシティ権、プライバシー権
広報実務では写真や映像・動画・音声などによる撮影、収録場面が多発します。印刷物としての各種広報誌やデジタル広報としてのWEB、SNSなど、幅広い広報制作物の素材として必要になるからです。一方、それらの活用度が高くなるほど、細心の注意を要します。
具体的には、撮影時および活用時において被写体となる個人の顔や、個人を特定できる関連情報の写りこみ(映り込み)への慎重な対応が迫られます。
広報担当者は、被写体となる他者の権利を侵害していないか「目配り」「気配り」「心配り」が試されますし、センシティブになるものです。それは肖像権・パブリシティ権・プライバシー権が絡んでくるからです。
ちなみに日本において肖像権・パブリシティ権・プライバシー権は、明確な法律(成文法)はなく裁判例が基礎となっています。
それぞれ明確な法律はないものの、文化庁ウェブサイトでは肖像権とパブリシティ権について、次のように説明されていますので紹介します。
「肖像権」は、自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利で、プライバシー権の一種とされています。また、芸能人やスポーツ選手等のように、著名人の氏名や肖像には一定の顧客吸引力があり、その価値に基づく権利のことを「パブリシティ権」と呼んでいます。ただし、我が国では法律で「肖像権」や「パブリシティ権」を規定したものはなく、これらの権利は判例によって確立された権利です。なお、我が国では、パブリシティ権の内容・効果・範囲・期間等については、まだ明確にはなっていません。また、実務上、芸能プロダクションに所属する芸能人の多くは、芸能プロダクションが「パブリシティ権」を管理する場合が多いと思われます。
■参考サイト:著作権テキスト(文化庁サイト内):
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94215301_01.pdf
また、プライバシー権についても日本での成文法が存在しないだけでなく、個人情報保護法との関連も深く、国の明確な情報を紐解くのは根気の要る作業です。
歴史的経緯や法解釈の変遷等、詳細な解説は法律の専門家に委ねるのが望ましいので、ここではポイントだけ紹介します。
- プライバシーの権利は、法的には幸福追求権を定める憲法第13条に由来する権利と解されています。
- 私生活をみだりに公開されないという権利(いわゆる私生活の平穏)として理解されてきました。その後、情報化の進展により、自己に関する情報の取扱いについて自己決定する権利・利益として理解されるようになっています。そして個人の私生活上の自由や秘密にしたい情報を保護する人格権の一種です。
- 個人情報保護法が知られていますが、本法は高度情報通信社会における個人情報の有用性に配慮しながら、プライバシーを含む個人の権利利益を保護することを目的とするもので、日本の個人情報保護の基本法です。
- プライバシーは個人情報よりも広い概念で、「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利」を含み、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含むようになっています。
参考サイトは内閣府所管の個人情報保護委員会とPマークポータルサイトとしました。
個人情報保護委員会は個人情報保護法を所管しています。
■参考サイト:
①個人情報保護委員会
②「個人情報」と「プライバシー」の違い(Pマークポータルサイト内)
それでは、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権の侵害を回避するために広報実務ではどのように向き合うのが望ましいでしょうか。最低限のポイントを紹介します。

■広報担当者としての実務上の対処
・撮影現場で動画・写真の撮影を実施することや撮影した動画・写真を広報誌や自社WEBサイト等に掲載することについて、被写体となる関係者から事前に同意をとっておくこと。
・可能であれば、書面等で利用条件を予め明確にしておくことが有効。
・広報用に掲載している従業員の写真や氏名等について、当人の退職等により使用できなくなる場合もある。
・法的な許諾を得ている場合でも、本人からの強い要望がある場合は対応することを想定しておく。
■肖像権ガイドラインについて
デジタルアーカイブ学会が公開している「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~」(2021年4月・ 2023年4月補訂)があります。
「本ガイドラインは、肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアーカイブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参考・下敷きにして頂くことを目的としている」としています。
ここで提示されている「ガイドラインのフローチャート」は、所蔵写真をインターネットその他の手段で「公開」する場面を想定するものですが、広報領域でも活用できるという見地が示されています。広報素材の肖像権チェックの活用場面で参考にしてみてください。
デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~」(2023年4月補訂)より
■生成AIに用いる入力時の注意点
前回AIと著作権について紹介しましたが、肖像権・パブリシティ権・プライバシー権の領域においても、生成AIサービスを介し、AI生成物の出力目的とした入力情報の取り扱いには権利侵害リスクが発生します。注意しておきましょう。
次回も続きます。
東京都中小企業診断士協会城北支部 広報部
田中尚美